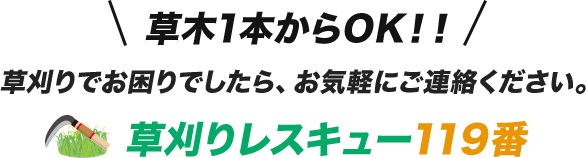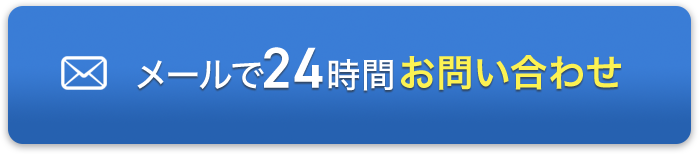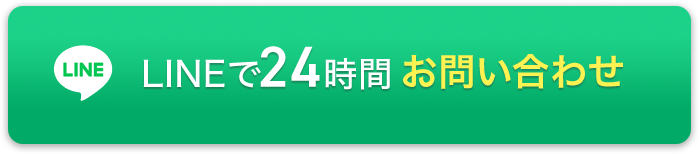お墓の草刈など解説!
草むしり問題の解決策ガイド。
はじめて草刈りを依頼、 【遠方にお住まいでお墓の除草ができない人の】お役立ち情報になれば幸いです。
1. 自分でお墓の草むしり・除草を行う

まずは可能な範囲で自力で対処する方法です。近距離に住んでいたり、まだ体力に自信がある場合は、自分自身で草むしりにチャレンジできます。メリット: 自分の手でお墓をきれいにできる達成感がありますし、費用も最小限で済みます(道具代や交通費程度)。他人に任せることへの抵抗感がある方でも、自力なら安心ですよね。デメリット: しかし体力的な負担は大きく、炎天下での除草作業は高齢の方には危険を伴います。また遠方に住んでいる場合は頻繁に通えないため、どうしても雑草が伸び放題になる期間ができてしまいます。
そこで自力で行う場合は、工夫して負担軽減を図ることが大切です。具体的な対策は後述の「実践的アドバイス」で詳しく解説しますが、例えば防草シートを敷いて砂利をかぶせる方法は経済的で効果的な雑草対策になります。一度敷けば長期間雑草が生えにくくなるので、次回来たときの草の量が格段に減るでしょう。他にも、伸びきった草は鎌(かま)で刈り取ってから根を抜く、除草剤も適宜活用するなど、次の草を生やさない工夫を凝らすことで毎回の作業を楽にできます。
2. 親族や知人に協力を依頼する

自分一人で難しい場合、家族や親族、地元の知人に頼む方法も考えられます。たとえば、お墓の近くに住む親戚や古くからのお知り合いがいれば、状況を説明して定期的に見に行ってもらえないか相談してみましょう。メリット: 身内や顔見知りに頼めると安心感がありますし、謝礼程度の負担で柔軟に対応してもらえる可能性があります。家族ぐるみで協力できれば「今回はうちが草むしりするから、次回はお願いね」というように持ちつ持たれつで管理していけます。デメリット: 一方で、頼まれた側にとっては手間や負担になることも事実です。高齢の親御さんに代わり子供世代が見ているケースでは、その子供世代も忙しかったり遠方だったりするでしょう。無理にお願いすると相手に気を遣わせてしまったり、自分自身も心苦しくなってしまうかもしれません。
この方法を取る場合は、お礼や感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。例えばお盆やお彼岸に帰省した際にみんなでまとめて掃除をしたり、その親戚に季節の贈り物を送ったりしてフォローしましょう。頼みっぱなしにならないよう、「次は自分が行くので大丈夫ですよ」と声をかけ合うだけでも相手の心理的負担は軽くなります。また、地元のお寺や墓地管理者と関係が良好であれば、「雑草がひどいようなら教えてください」とお願いしておくのも一つの手です。管理者によっては簡単な除草なら対応してくれる場合もありますし、難しければ次に紹介する専門サービスを教えてくれることもあります。
3. 墓掃除・お墓参り代行サービスを利用する

現在もっとも注目されている解決策が、プロのお墓参り代行サービスを利用する方法です。これは高齢や遠方、仕事が忙しいなどの理由で自分でお墓参り・掃除が難しい人に代わって、専門のスタッフが現地でお墓のお手入れをしてくれるサービスです。近年では石材店や清掃会社、シルバー人材センター、さらにはNPO法人まで様々な団体が参入しており、サービスの選択肢が広がっています。
**具体的に何をしてくれるの?**と思われるかもしれませんが、一般的な代行サービスの内容はほぼ共通しています。例として、くらしのマーケット(生活サービスのオンライン仲介)に掲載されているお墓参り代行の標準作業を見てみましょう。
- 作業前の合掌礼拝(お墓の前でお参りを開始する旨をご先祖に報告)
- 清掃前の写真撮影(現状を記録)
- 枯れた花やゴミの撤去処分
- 墓石・外柵や付属品の拭き掃除(水鉢、花立て、香炉、灯篭などをきれいにします)
- 敷地内の雑草取り(生えている雑草を根から抜き取ります)
- お水・新しいお花・お線香のお供え(依頼内容による)
- 作業後の写真撮影(掃除が完了した状態を記録)
- 最終報告と合掌礼拝(終了のご報告とお参り)
依頼主には後日ビフォーアフターの写真や作業報告書が届けられるので、遠くからでもお墓が綺麗になった様子を確認できます。料金は業者や依頼内容によって幅がありますが、1基あたりおよそ8,000~12,000円が相場です。簡易清掃のみなら7,000円前後~、墓石のコーティングや特別なクリーニングを含むプランでは2万円近くになることもあります。
メリット: プロに任せる最大の利点は、なんといっても確実で丁寧な作業です。自分では半日かかる草むしりも、慣れたスタッフなら短時間で綺麗にしてくれますし、掃除道具も本格的です。また写真報告があるため「本当にちゃんと掃除してくれたの?」という心配もありません。忙しい方でもワンクリックで予約でき、日程もこちらの希望に合わせてもらえる柔軟さも魅力です。さらに、近年はオンライン墓参りに対応したサービスも登場しています。例えば大手ブライダル企業が運営する「きたよ。」という代行サービスでは、スタッフが現地からビデオ通話をつないでくれて、あなたは画面越しに一緒にお参りできるプランもあります。実際に訪れられなくても、掃除の様子やお墓の現在の状態をリアルタイムで共有してもらえるのは嬉しいポイントです。
デメリット: 一方で、やはり費用負担は避けられません。定期的に頼むとなれば年間で数万円の出費になります。また「他人に先祖供養を任せる」ことに抵抗を感じる方もいるでしょう。しかしその点はサービス提供側も配慮しており、スタッフは礼儀作法をわきまえ真心を込めて対応してくれます。実際、先述の「きたよ。」ではサービス開始からわずか数年で累計600件以上の依頼を受け、利用者満足度は99%超と極めて高い評価を得ています。リピート利用するお客さんも初年度から30%にのぼるとのことで、多くの人が「頼んで良かった」と感じている証拠でしょう。
代行サービスを利用する際の心配として「どの業者に頼めばいいかわからない」「悪徳業者にあたったらどうしよう」という不安があるかもしれません。そこで信頼できる業者の選び方として、以下のようなポイントをチェックしてください。
- 実績や口コミ: インターネットの口コミサイトや比較サイトで評判を確認しましょう。くらしのマーケットなどでは実際の利用者レビューを星評価で見られます。
- 運営母体: 石材店や上場企業、老舗仏具店、自治体関連(シルバー人材センターなど)といった信頼性の高い団体が運営しているサービスは安心感があります。「シルバー人材センター」では全国各地でシニアスタッフがお墓掃除代行を行っており、墓石の拭き掃除や草取り、写真報告まで基本プランに含めて丁寧に対応してくれます。
- 料金体系の明示: Webサイト等で作業内容と料金が明確に示されているか確認しましょう。相場より極端に安い場合は追加料金が後から発生しないか注意し、逆に高額すぎる場合は内容を精査してください。
- 問い合わせ対応: 質問した時のレスポンスや説明が丁寧かどうかも重要です。親身に相談に乗ってくれる業者はトラブル時の対応も期待できます。
4. 永代供養墓・墓じまい等を検討する

最後に、少し極端な選択肢かもしれませんが、根本的な問題解決策として「お墓自体の管理方法を変える」ことにも触れておきます。どうしてもご家族・ご親族で今後お墓を守っていくことが難しい場合、永代供養墓への移行や墓じまいを検討する人も増えています。永代供養墓とは、個人や夫婦の遺骨を寺院や霊園が半永久的に供養・管理してくれるお墓のことで、一度納めれば遺族に日常的なお墓の手入れ負担がかかりません。最近の調査では「後継ぎ不要のお墓を選んだ」という人が64.1%にも上り、時代を象徴する傾向となっています。まさに「子や孫に負担をかけたくない」という思いから、最初から永代供養タイプを選ぶ人が増えているのです。
また、今あるお墓を整理して墓石を撤去し、ご遺骨を別の供養方法に移す墓じまいも年々増加しています。婚礼大手の企業が墓じまい手続きの代行サービスを始めたというニュースもあり、少子高齢化の中で避けられない流れと言えるでしょう。墓じまいには行政手続きや費用の問題があり簡単ではありませんが、「この先本当にお墓を維持できない」「遠くて誰も足を運べない」という場合の最終手段として頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
メリット: 永代供養墓に移行すれば雑草の心配から完全に解放されますし、墓じまいをすれば後の管理負担もゼロになります。デメリット: とはいえ、ご先祖代々のお墓を手放すことに抵抗や寂しさを感じる人も多いでしょうし、費用もそれなりにかかります。現時点で迷っている段階なら、無理に今決めず、まずは上記の代行サービスなどで現状維持を図りながら、ゆっくり家族と話し合うことをおすすめします。「いずれ墓じまいも視野に」という場合でも、それまでの数年間をどう乗り切るかという問題は残りますから、その間の草むしり対策は必要だからです。
以上、状況に応じた4つの解決策をご紹介しました。次のセクションでは、実際に草むしり・除草を行う際の具体的な手順やコツ、注意点をさらに掘り下げていきます。
実践的アドバイス

このセクションでわかること: 解決策を実行に移すための具体的な手順、テクニック(道具の準備、作業時期・頻度のポイントなど)、よくある失敗パターンとその回避法、成功事例や体験談
ここからは、今日から役立つ実践的なアドバイスをお届けします。自力で草むしりをするにせよ、業者に依頼するにせよ、知っておくと得するテクニックや注意点を押さえておきましょう。
● 草むしり作業の基本ステップ
自分でお墓の草むしりに臨む場合、闇雲に始めるより手順を決めて段取り良く進めるのがコツです。一般的なお墓掃除・除草の流れをまとめると次のようになります。
- 準備とお参り開始の挨拶: 墓前に立ったらまず軽く合掌し、「これからお掃除させていただきます」と心の中で声をかけます。作業前に手を合わせることで気持ちが落ち着き、安全祈願にもなります。
- 枯れ花・ゴミの片付け: 花立てに残った古いお花や落ち葉、ごみを集めて処分します。持参したゴミ袋に入れ、後で持ち帰るか指定のゴミ箱に捨てましょう。
- 雑草の除去: いよいよ草むしりです。伸び放題の場合は鎌で根元から刈り、その後残った根を丁寧に抜き取るようにします。根っこがちぎれると再生しやすいので、根元近くの土を少し掘り起こしてから抜くと良いでしょう。雑草抜きは代行サービスでも標準作業に含まれる重要工程です。
- 墓石・付属品の掃除: 雑草とゴミを取り終えたら、桶に水を汲んで墓石や花立て、水鉢、香炉(線香立て)などを洗浄・拭き掃除します。スポンジや柔らかい布を使って汚れや苔を落としましょう。力を入れすぎると石を傷めることがあるので優しく磨きます。苔がひどい場合は専用洗剤を使うか、無理せずプロに任せる判断も必要です。
- 仕上げとお供え: 周囲をほうきで掃き清め、持参した生花やお線香をお供えします。花立てには水を入れ、新しいお花を生けてください。最後にもう一度手を合わせ、今日のお墓掃除が無事終わったことをご先祖様に報告します。
以上が一連の流れです。一度覚えてしまえば次回からスムーズに進められるでしょう。所要時間は雑草の量にもよりますが、一人なら1~2時間、家族と手分けすれば30分程度で終わることもあります。
● 草むしりの便利グッズと服装

作業効率と安全のために、持って行くべき道具や服装にも気を配りましょう。以下はおすすめの持ち物リストです。
- 作業手袋(軍手): とげのある雑草や汚れから手を守ります。滑り止め付きがベター。
- 草刈り鎌・根切り用具: 小型の草刈り鎌は必携です。根を抜きやすいよう先が細い「雑草取りフォーク」やスコップがあると根ごと掘り起こすのに便利。
- ゴミ袋・ちりとり&ほうき: 抜いた雑草やゴミを入れる袋は丈夫なものを。墓石の周りを掃くホウキとちりとりもあると仕上げが綺麗です。
- バケツとスポンジ・雑巾: 水を汲んで墓石や装飾品を洗うためのバケツ。洗浄用スポンジと拭き上げ用の雑巾も用意しましょう。
- 膝あて・レジャーシート: 長時間しゃがむ場合は膝をつく部分に敷くクッションやシートがあると膝が痛くなりません。
- 帽子・飲み物・タオル: 夏場は必須の熱中症対策グッズ。帽子や日よけ、こまめな水分補給用の飲み物、汗拭きタオルを準備。虫よけスプレーもあると安心です。
- 除草剤(必要に応じて): 根絶やしにしたい雑草が多ければ、環境に優しいタイプの除草剤も持参しましょう。ただし使用は説明書を守って慎重に。
服装は長袖・長ズボンが基本です。夏でも肌の露出は控え、薄手でも良いので長袖シャツに動きやすい長ズボンを着用してください。軍手+長袖で腕を、帽子+タオルで首筋をガードすることで、日焼けや虫刺され、擦り傷のリスクを減らせます。足元もサンダルは避け、滑りにくいスニーカーや長靴を履きましょう。草むしり中に誤って石を落として足に当たることもあるので、つま先の保護にもなります。
● 作業の適切なタイミング・頻度

いつ頃草むしりすべきかも重要なポイントです。おすすめは春と秋の涼しい季節。具体的には、雑草が伸び始める前の**春彼岸(3月)頃と、夏の生育期を過ぎた秋彼岸(9月)頃の年2回が最低ラインです。この2回に加え、可能であればお盆前(7~8月)**にも一度手入れしておくと安心でしょう。実際、多くの方がお盆や彼岸、年末年始といった節目に合わせてお墓を掃除しています。
ただし遠方に住んでいると頻繁には行けませんから、年1回になってしまう場合もあります。その場合は、梅雨前の初夏か秋の終わりなど、比較的過ごしやすい時期を選びましょう。真夏の炎天下や真冬の凍える時期は避け、無理のない範囲で計画を立ててください。
また、草むしりの時間帯も大切です。夏場であれば朝のうち(~10時頃)か夕方に作業するようにします。日中の猛暑時に作業すると熱中症の危険がありますし、地面が熱せられていて体力を奪われます。朝夕なら気温も比較的低く、雑草も夜露や朝露で柔らかく抜きやすいという利点もあります。逆に早朝過ぎると周囲が静まり返っていて物音が気になったり、夕方遅いと暗くなって作業しづらいので、その土地の環境に合わせ調整してください。
● 雑草を生えにくくする予防策
せっかく頑張って草むしりをしても、またすぐ雑草が生えてきては苦労が水の泡ですよね。そこで雑草の発生を抑える予防策も取り入れてみましょう。既に少し触れましたが、防草シートや固まる土など、代表的な方法をいくつか紹介します。
- 防草シート+砂利: 最もポピュラーで手軽な方法です。雑草を除去した後、土の部分に防草シートという厚手のシートを敷き、その上から玉砂利を敷き詰めます。シートが太陽光を遮り雑草の繁殖を防ぐため、長期間にわたり草が生えにくくなります。シートはホームセンターで数千円程度(小面積なら3,000円前後~)で購入可能です。初期費用はかかりますが効果は絶大で、**「10年間雑草とおさらば!」**とうたう商品もあるほどです。デザイン的にも白やグレーの砂利がお墓に特別感を与え、防草と景観の一石二鳥です。
- 固まる土(防草土): 土に混ぜて水をかけると固まる特殊な土です。施工すると地表がコンクリートのように固まりますが、透水性がありヒビ割れしにくい性質があります。見た目は土に近く自然ですが雑草の種子が発芽しにくく、長期間草を抑制します。防草シート同様に近年人気で、砂利と併用も可能です。
- コンクリートで舗装: 思い切ってお墓周りの土部分をコンクリートで埋めてしまう方法です。物理的に草が生える場所をなくすので最も確実ですが、費用が高くつきますし、一度固めると元に戻すのが大変です。外観も無機質になりがちなので、よほど雑草に悩まされている場合の最終手段と言えます。なお最近はコンクリより石板を敷き詰める家も増えています。見た目に高級感がありますが雨天時に滑りやすいので注意が必要です。
- 除草剤の定期散布: 根本的な解決ではありませんが、除草剤を定期的に撒くのも効果的な予防策です。液体タイプはピンポイントで小面積向け、粉末(粒状)タイプは広範囲に散布して地中で雑草を枯らすのに適しています。春先や草の成長期に合わせて撒いておけば、草むしりの頻度を減らせるでしょう。ただし効果が永続するわけではないので、「生えてきたら撒く」を繰り返す必要があります。環境に配慮した製品や、土壌に影響を残さないタイプもありますので、用途に合わせ選んでください。
これらの対策は、それぞれ単独でも有効ですが組み合わせるとより万全です。「防草シート+砂利+必要に応じて除草剤」のトリプル対策などは、多くの霊園で採用され雑草に悩まなくなったとの声もあります。また新しくお墓を建てる際には、最初から石板張りやコンクリ敷きをオプションでお願いする家も多いです。今のお墓に手を加えるのが難しい場合でも、草が生えにくい環境づくりという視点を持つことで、将来の手入れがぐっと楽になるでしょう。
● よくある失敗とその回避方法
次に、草むしり・除草作業で陥りがちな失敗例と、その防止策を紹介します。先人たち(?)の失敗に学び、賢く立ち回りましょう。
- 失敗例1: 夏の正午に作業して熱中症に…
回避法: 繰り返しになりますが作業時間は選びましょう。気温・日差しがピークの時間帯の作業は厳禁です。どうしてもその時間しか無理なら、日陰で休憩を取りながら短時間で切り上げるか、無理せず代行サービスに任せる勇気も必要です。熱中症対策グッズ(経口補水液や冷却タオル)も準備しておくと安心です。 - 失敗例2: 腰を痛めた・膝が痛くなった
回避法: 長時間中腰や正座で草むしりをすると腰や膝に負担がかかります。膝あてクッションや小さい折りたたみ椅子を使って、楽な姿勢で作業しましょう。こまめに体を伸ばしたり、水分補給して休憩することも大事です。「今日はここまで」と割り切り、全部やりきろうとしないことも長続きのコツです。 - 失敗例3: 抜いた雑草を放置して帰ってしまった
回避法: 抜き取った雑草や落ち葉は必ず持ち帰るか処分場へ捨てましょう。山積みに放置すると、そこから種が飛んで再び雑草の温床になってしまいます。ビニール袋を二重にするなどして、車で持ち帰る際に泥や虫が漏れないよう配慮すると良いです。もし現地にゴミ箱があっても、生ごみ扱いで持ち帰りがルールの所もあるため、墓地の規則に従ってください。 - 失敗例4: 石材を傷つけてしまった
回避法: 墓石や周辺の外柵を傷つける原因として、硬い金属ブラシでゴシゴシ擦ったり、尖った道具で苔を削り落とそうとするケースが挙げられます。石材は意外とデリケートなので、基本は柔らかいスポンジと水洗いで汚れを落とします。こびりついた苔は無理に取ろうとせず、墓石専用クリーナーやプロのクリーニングに任せるのが無難です。また、狭い隙間の雑草を取る時などに金具を差し込むと、石と石の継ぎ目を傷めることがあります。竹製のヘラなど、柔らかい素材の道具で代用しましょう。 - 失敗例5: 業者に頼んだら期待と違った
回避法: せっかくお金を払って依頼したのに「ここまでやってほしかった」というミスマッチが起こることも。これを防ぐには事前の打ち合わせが重要です。たとえば「敷地の隅に植木があるがそれも剪定してほしい」といった希望は最初に伝えましょう。多くの代行サービスは標準プラン以上の対応も可能で、「きたよ。」では雑草処理以外に植木の枝切りや落ち葉掃除など利用者の幅広い要望に応えている実例があります。つまり言えばやってもらえることも多いので、遠慮せず希望を伝えることが大切です。また実績豊富な業者は繁忙期でも安定したサービスを提供しますが、小規模なところはお盆前に予約が殺到して手が回らなくなる場合もあります。早め早めの予約と連絡で、余裕を持って依頼しましょう。
● 利用者の声・成功事例
最後に、実際にお墓の除草問題を乗り越えた成功事例や体験談をご紹介します。
- ケース1: 遠方在住のAさん(60代女性)の場合
「実家のお墓が車で5時間以上の遠方にあり、年1回行けるかどうかでした。ある年、お盆に行けず数年ぶりに訪ねたら雑草が背丈ほどに…途方に暮れていたところ、娘に教わったお墓掃除代行サービスを初利用しました。正直『お墓の掃除をお金で頼むなんて』と迷いましたが、届いた清掃後の写真を見て驚きました。見違えるほど綺麗になっていたんです。それ以来、お彼岸や命日には業者さんにお任せし、私自身は年末に一度だけお参りに行くスタイルに変えました。お墓を前にしたとき「今年も綺麗にしてもらって良かったね」と手を合わせると、以前より心穏やかに向き合えている気がします。」 - ケース2: 地元在住のBさん(70代男性)の場合
「自宅からお墓までは車で30分ほどなのですが、高齢で足腰が弱くなり草むしり作業が辛くなってきました。息子たちは皆県外で忙しいため、自分なりに工夫しようと防草シートを敷いてみることに。園芸店で教わりながら敷いたところ、翌年から雑草の量が激減してびっくり。完全になくなるわけではありませんが、伸びるスピードが違います。そのおかげで、今ではお盆とお正月前の年2回の軽い掃き掃除と草取りだけで十分間に合っています。かえって息子たちも『綺麗にしてあるね!』と感心するほどで、手入れ負担を減らしつつ墓所を良好に維持できて一石二鳥でした。」 - ケース3: 都内在住のCさん(50代女性)の場合
「夫の実家のお墓が田舎にあり、義父母も高齢でお墓掃除に行けなくなりました。私自身も働いているため頻繁には行けず悩んでいましたが、地元のシルバー人材センターに相談したところ、ほぼボランティア価格でお墓掃除を請け負ってくれるとのこと。シルバーさん(地域の高齢スタッフ)の丁寧な仕事ぶりに義父母も感激し、『助かった、これからもお願いしよう』と喜んでいました。地元密着なので安心感もありますし、困ったときは地域の力に頼るのも大切だと実感しました。」
これらの事例からわかるように、状況に合った方法を選べば必ず解決の道は開けます。 大切なのは「自分一人で抱え込まないこと」。サービスを上手に活用したり、道具や予防策に投資したりすることで、高齢や遠方といったハンデを乗り越えてお墓をきれいに守っていくことができるのです。
よくある質問と回答 (FAQ)
Q: お墓の草むしりは最低どのくらいの頻度ですればいいですか?
A: 理想は年2~3回程度です。多くの方が春彼岸・秋彼岸・お盆前に合わせて計2~3回手入れしています。難しければ少なくとも年1回は行い、その際に防草シートや除草剤で対策しておくと次回まで草の伸びを抑えられます。
Q: 真冬や真夏でも草むしりは可能でしょうか?
A: 可能ではありますが、あまりおすすめできません。真夏の作業は熱中症の危険があり、真冬は寒さで体が動きにくく作業効率も落ちます。どうしてもその時期に行うなら、夏は朝夕の涼しい時間帯、冬は暖かい日中を選び、防寒・暑さ対策を万全にしてください。
Q: 雑草対策に除草剤を使っても大丈夫ですか?お墓に悪影響は?
A: 適切に使えば問題ありません。除草剤は墓石自体には基本的に影響しませんし、最近の製品は土壌に残留しにくく安全性も向上しています。ただし撒きすぎは周囲の植物を枯らしてしまうので注意しましょう。液体タイプはピンポイント処理、粒状タイプは広範囲の予防向きです。使用後しばらくは新しい花を植えられない場合もあるので、墓所の環境に合わせて使い分けてください。
Q: お墓掃除代行サービスの料金相場や頼み方を教えてください。
A: 一般的な相場は1回あたり8,000~12,000円前後です。内容によりますが、簡易清掃のみなら1万円以下、献花や墓石コーティング込みだともう少し高くなります。頼み方は簡単で、ネットや電話で予約するだけです。例えば「くらしのマーケット」のお墓参り代行ページではエリアと日時を選ぶと、利用可能な業者一覧と料金が表示され、口コミを見ながら予約できます。直接業者の公式サイトから申し込む場合も、お墓の場所や希望日を伝え、プランを選ぶだけです。当日は立ち会い不要で、後日報告を受け取れます。
Q: 地元に知り合いも業者もない場合、何か支援策はありますか?
A: 地域によっては自治体やボランティア団体の支援があります。例えば各地のシルバー人材センターでは、お墓掃除の仕事を請け負っていることがあります。費用も比較的安価です。また、お寺によっては有志で墓地清掃ボランティアを募っている場合もあります。自治体の広報やお寺の掲示板などをチェックしてみましょう。それでも難しければ、先述の全国対応の代行サービスを利用するのが確実です。
Q: 雨の日に草むしりしてもいいのでしょうか?
A: 小雨程度ならメリットもあります。土が湿っていると雑草の根が抜きやすく、埃も立ちにくいです。ただし大雨や前日までの雨で地面がぬかるんでいる時は足元が滑りやすく危険ですし、泥で掃除がかえって大変になることも。雨天時に作業する場合は滑り止め長靴を履く、雨合羽を着るなど安全に配慮してください。雷の恐れがある時は絶対に中止しましょう。
Q: お墓参り代行を利用するとご先祖様に失礼ではありませんか?
A: そのように心配されるお気持ちはもっともですが、現在では多くの方が事情により代行サービスを活用しています。大切なのは「お墓を大事にしたい」というあなたの気持ちであり、実際に手を動かすのが誰であれ、お墓が綺麗に保たれることにご先祖様も安心されるはずです。サービス担当者も心を込めてお参り・清掃してくれますし、利用者からも「頼んでよかった」「これで心配事が減った」との声が多く聞かれます。むしろ何年も放置して荒れた状態にしてしまう方が、ご先祖様も悲しまれるのではないでしょうか。遠慮や罪悪感を感じる必要はありませんので、今できる最善の方法で供養の心を形にしていきましょう。
Q: 将来的に自分の代でお墓の管理が終わってしまうかも…。今からできる準備はありますか?
A: 少子高齢化の中、「自分たちの代で墓仕舞い(墓じまい)するかもしれない」という方は増えています。その場合でも慌てる必要はありません。永代供養墓などの情報収集をゆっくり始めつつ、現在のお墓はきちんと管理を続けることが大切です。墓じまいの手続きには時間も費用もかかりますし、親族間での合意形成も必要です。それまでの間、今回紹介したサービスや対策でお墓を良好に維持してください。心の区切りとして、最後に墓じまいする前にプロに徹底清掃してもらいピカピカの状態でお別れする、という方もいます。それも一つの供養の形でしょう。いずれにせよ、「終わりを見据えて今をないがしろにしない」ことが後悔を残さない秘訣です。
以上、よく寄せられる疑問にお答えしました。他にも気になる点があれば、お近くの石材店や信頼できるサービス業者に遠慮なく相談してみてください。あなたのお墓管理の不安が少しでも和らぎ、安心して日々を過ごせるよう応援しています。
お墓の除草の料金について
定期的な管理も対応!
お墓の除草の基本的な費用
お墓の雑草対策はおまかせ


- お墓の除草(草むしり、除草剤)
草刈りレスキューは費用が安い! - 1坪:3.3㎡(畳2枚分)
基本料金3,000円~からで安心です! - 面倒なお墓の除草、管理を(プロにお任せ)
定期的なお墓の手入れもお得です!
草刈りレスキューの基本費用
| お墓の除草の基本料金 | 1坪あたり3000円~ |
| 見積費用 | 無料 |
| 交通費・出張費用 | 無料 |
| お墓の除草の時期 | 春、初夏、お盆やお彼岸、秋、冬前 |
費用はどのくらいかかる?
お墓の除草費用

お墓の除草の場合、除草面積をもとに費用を算出します。
一坪当たり3,000円~のご案内となります。
また、お墓の除草だけでなく、お墓の清掃サービス、お墓参り代行サービスも承っております。
お墓の清掃サービス

なかなかお墓参りや清掃に行くタイミングがない方、夏場で長時間外に出るのが危険な時などからは、お墓の清掃代行サービスもご利用いただいております。
墓石、墓誌、花立、香炉など対応可能です。
お墓参り代行サービス

ご高齢のお客様や、遠方に住んでいるお客様向けに、お墓参り代行サービスも合わせて対応可能です。献花、お線香、合掌、拝礼、墓石の清掃、雑草取りなど全て対応可能です。
スタッフから写真で報告致しますので、ご安心してご依頼ください。
お墓の除草は、作業範囲やその他サービスを併用するかどうかで費用が変わります。まずはお気軽にお問い合わせください。
お墓の除草が難しいあなたへ:草むしり問題の解決策ガイドを解説!
お墓の除草?、 【どうすればいいのか?を知りたい】そんなお悩みを解決する!お役立ち・頼りになる・草刈り業者としてご利用いただければ幸いです。
お墓の草刈りにお困りなら!お草刈りレスキュー119番
北海道・東北エリア
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 仙台市 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東エリア